2か月あった夏休みof人生の夏休みもついに終了です!漕いで食べて遊んで寝るだけの生活が終わってしまう……😭春休みに期待!!
初めまして!1回生漕手の原颯太郎(はらそうたろう)です。新人のブログの担当は名簿順で当たっています。私は「は」から始まる名前なので真ん中くらいかと思っていましたが119期は早い名前が多くて,意外と最後の方で驚いています。これを書く前も書きながらも,先輩のブログや同期のブログを沢山読んでいますが,皆さんの個性が出てて本当に面白いですね。自分もあんな面白くて読みやすい文章が書けたらなあと思って読んでいます。私は,思考の流しそうめんのような文章を書きます。良いのが流れてきたら取って食べる。カラフルなそうめんが流れてきます。そうめん以外も。それを取って食べずに置いといて,ある程度溜まったら綺麗な順番に食べるとか,そういうことはしません。回転寿司ではなくて流しそうめんなのはそういう理由です。つまりこれは,文章の構成力や要約力が無いことの言い訳になるわけですが,今書いているのは小論文でなくてブログだからそれでいいじゃないかという感じです。でも自分のブログにどんな意味があるかはよく分かってません。部員が読むのは想像がつきますが,他大のボート部員が読んでるかもしれません。OBさんが読んでくれてるかもしれません。親が読んでるかもしれません。引退前の自分が読んでたり,あるいは,もしかしたらローイングにやる気を見いだせなくなった自分が初心を振り返るために読んでたりするかもしれません。逆に,誰も読まないかもしれません。いずれにしても,私は自分の書いたということに価値を見出します。今の時代,全部ChatGPTとかGeminiとかClaudeとかそういうやつに突っ込んで何かしらの要望を付ければ私の書いた何倍も読みやすい文章が出てくるのは知っています。もしかしたらブログの提出期限が迫ってきて,めんどくさくなってそういうのに頼ってる人もいるかもしれませんが,私はそれを批判するつもりはありません。新しい時代の文章の書き方の1つだと思うからです。ただし自分が書くやつは,個人的にそういうのに頼りたくないというだけです。無理に尖ろうとしたり,丸くなろうとしたりしたくないんです。
さて,今回は初めて書くブログなので自己紹介をしてみようと思います。私は滋賀で生まれ,滋賀で育ちました。生まれて18年間ずっと滋賀です。と言っても,実家は琵琶湖から結構離れてるので,自分が滋賀県民であると強く感じたり,琵琶湖に誇りを持つようになったのは実は高校からです。県立の膳所高校を卒業して工学部の情報学科に入学しました。情報学科に入ったのは,数学と物理が好きだったのと,高校の探究という科目で強化学習(機械学習の手法の1つで,機械にゲームをさせられます!!)について勉強したり,発表したりするのが楽しかったからです。小学校高学年くらいから高校2まで,明確な将来の夢というものが見つけられず,将来の夢を言う必要のある時は金持ちとか総理大臣とか,関西に自作キーボード専門店を作るとか適当なことを言ってやり過ごしていましたが,この経験を通して明確に研究者になりたいと思うようになりました。膨大なデータ,時間,電力を使う機械の学習と,柔軟で効率のいい人間の学習の違いに凄く興味があって,機械学習と神経科学の両側のアプローチでそれに迫る計算論的神経科学を研究したいと思っていました。しかし大学に入学してからは,数理工学の世界の広さを知り,他にも面白い分野があるかもしれないとか,計算論的神経科学は人気な分野だから自分の頭脳でやっていけるのか心配になってきたとか,色々思うようになって,今は研究したい分野は決まっていないのに研究者になりたいという,好きな人がいないのに彼女が欲しいというのと全く同じ状況になっています。そして何よりエネルギーの大半をローイングに費やしていて,高校時代よりも勉強する余裕がないです。でも今はまだその時ではないだけで,その時が来れば一生懸命勉強するつもりはしています。今はひたすらボートを漕いでいたい。高校時代の部活も,ボートをやっていました。それも,琵琶湖やここ瀬田川で!!したがって,漕歴及び瀬田川歴は4年目になります。だからといって,漕ぎが上手かったり,エルゴがめっちゃ回ったりというわけではありません。大学で再び1からスタートするぞ,という気持ちで入部して,日々練習しています。
ボート以外で好きなことは,食べること,サウナとか風呂に入ること,合宿所の3階でごろごろすること,麻雀,ゲーム,音楽を聴くこと,勉強すること,カラオケなど色々ありますが,どれも中途半端です。自分だけではないと思いますが,趣味とか好きなことを聞かれたときに,好きは好きだけどそれほど熱中はしていないことを答えるのって,少々抵抗がありますよね。例えばゲーム,中学時代は朝から晩まで画面に向かっていましたが,今は時々エッセン部屋で同期とみんはやで遊んだり,3階のミニファミコンをやったりするぐらいで,全くやらない日も多いです。学生の本分である勉強,あれだけやりたかった勉強でさえ,夏休みはほとんど出来ていませんし,前期も部活や恋で頭がいっぱいで中々手が回りませんでした。

それでもやはり,好きなものは好き,と積極的に言うようにしています。でないと,よほど熱中できるものに出会えなかったときに,好きなことをするための人生において好きなことがないという,恐ろしい状態に陥ってしまうからです。また,自分が何かを好きと認め,それを宣言することでより「好き」が確実になるとも考えています。エルゴだって,高校時代は世界一憎いとまで思っていましたが,最近はちょっと好きかも!と思う瞬間が増えてきています。乗艇もますます好きになってきました。いい感じです。あと最近,FRUITS ZIPPERがめっちゃ好きです。9月13日には休養中だった月足天音さんが復帰することが発表され,大いに盛り上がりましたね。私は2000TTでベストを更新した直後にそのアナウンスを見て,ものすごく嬉しくて,幸せな気持ちになりました。エッセンの洗い物じゃんけんに勝った時など(119期では勝者が全員分を洗うルールです),曲を聴きながら楽しく皿を洗っています。FRUITS ZIPPERは,「何でもかんでもかわいいんだもーん」という歌詞にあるように,周りと違ったり,うまくいかなかったりしても,生きているだけで,”NEW KAWAII”として全てを受け入れてくれるような曲が多く,自己肯定感が本当に上がります。これまでアイドルなんて近所のおっさんおばさんみたいに見分けのつかない人達の集まりで何がいいのか全く分かりませんでしたが,しんどい時期にたまたま聴いた曲で救われてからは,考え方が180度変わりました。エルゴの時にも,ハードでアップテンポな曲に数曲混ぜて聴いています。普段はイヤホンをするか他の人の流す曲を聴いていますが,以前自分がスピーカーに繋いだ時にシャッフル再生で「すーぱーかれんたいむ」が流れてしまい,数名から苦情を頂きました。申し訳ありませんでした。今回はたまたまでしたが,私は自分の好きを人に押し付けることは極力しないようにしています。自分がそうであるように,人に勧められても結局好きになるのは自分のタイミングですから,軽く勧める所までしかしません。その点において,新歓はかなり難しそうです。自分がボート部が大好きでも,新入生に強く迫ってしまったら逆効果ですので勧めることまでしかできず,もっとボート部の良いところを伝えたい!!と,もどかしい思いをしそうです。

話が大分それてしまいましたが,丁度新歓が出てきましたので,私がボートをするようになったきっかけと,京大ボート部に入ったきっかけについても書こうと思います。3年前,高校入学時の私はどの班活動に入ろうか全く候補もありませんでした(膳所高校では部活動のことを班活動と呼ぶ,という恐らく先輩方からすればもう何度目か分からない注釈)。中学はサッカーをしていましたがそれほどやる気も見いだせず続ける気もありませんでしたので,どうしようかと思っていたところ,席が隣で後の大親友となる人がボートが気になると言っており,そこでボート班の存在を知りました。丁度自分のいた1年9組の隣の空き教室でボート班の説明会をやっていたので,帰るついでに寄ってみました。どんな話をされたかはあまり覚えていませんが,とにかく強い!!というのをアピールされたのを覚えています。確か大量の実績を見せられて,「野球で言うたら大阪桐蔭みたいな高校なんやで」と言われた気がします。説明を聞くだけではボートの魅力はあまり感じませんでしたが,試乗会があると言われたので,数日後に行きました。付きクォドに乗せてもらい,水上を疾漕する気持ちよさに感動しました(後にそれは5cmローだったと明かされましたが,とにかく速く感じたんです!)。加えて班の雰囲気が本当によく,他の班を1つも見ていないにも関わらず,勢いに任せて入班を決めました。これが人生でした最もいい決断の1つでした。何も知らないからこそできた,最高の決断でした。
私は小学校くらいから運動全般に苦手意識がありました。走るのが遅いのと,いわゆる運動神経が悪く,球技系がかなり苦手でした。野球,バスケ,ドッヂボール,テニスとかが出来なくて,やっていたサッカーでさえ人並み以下な気がします。これではスポーツそのものが向いてないと思い込んでいました。ところが,ローイングで求められる力は他のスポーツとは違うということに,入班してちょっとしてから気づきました。勿論,私はローイングの世界でトップレベルの体格や心肺を持っているわけではありませんが,それでもその当時の周りの中ではエルゴが回る方でした。幸い自分は体重が付きやすい方で,当時脚の太さも人並み以上ではありました。もしかしたら自分が少しでも活躍できるスポーツに出会えたかもしれないというのが本当に嬉しかったのを覚えています。この,自分でも上に行けるかもしれないという認識をして初めて,スポーツを「頑張る」ためのスタート地点に来ることが出来ました。
高校の約2年半,ローイングを通してたくさんの出会いがあり,負ける悔しさと勝つ嬉しさ,仲間の大切さを学び,私の人生は変わりました。部活というものがこんなにも楽しくてやりがいのあることだと気づけました。ボート班に入ったことに何一つ後悔はありません。

今年の3月。高校を卒業してしばらくした頃,高校の先輩である日生下さんからボート部を紹介されました。しかし今度はボートのしんどい部分,主にエルゴとか,エルゴ等を知っていましたし,週5,6日のハードな生活で他のことをする余裕もないだろうと思ったので,入るつもりは全くありませんでした。大学では,運動はしたいけどほどほどにして,学問漬けの生活を送る予定でした。実際入学当初は本当に勉強にしかモチベーションがなくて,一週間の一番の楽しみが「数理工学概論」の講義,という状態でした。それでも久しぶりに瀬田川でボートを漕いでみたいし,すき焼きもタダで食べられるので,ボート班の同期と新歓への参加を決めました。新歓だけのつもりでした。とは言ってもこの時,すでに4月も後半で,その同期は某サークルへ既に入サーしていたのに対し,私は色々回ってみたものの,まだどこにも決められていなくて少し焦っていました。様々な新歓に参加しては,活動内容はめちゃくちゃ興味あるのに,何か違う気がする…と感じていました。そして,何をするかと同じくらいどんな人達とするかも大事だなあと考えるようになりました(確か,長嶋さんのブログに同じことが書いてあったような)。高校は1クラスしかないコースに通っていたので3年間クラス替えはありませんでしたし,ボート班も学校から少し離れた所に艇庫があり,独自の文化を築いていました。要するに私は,高校時代に過ごした,カルピスの原液,或いは凍らしたアクエリの最初の方に溶けてくる部分みたいな,濃い濃い人間関係を求めていたのです。学科の友達とは一緒に授業を受けたりご飯を食べたりするけど,休日までずっと一緒にいるわけでもない。活動頻度の低いサークルにいくつか入って,広く浅い交友関係を広げられるだろうか?何かに打ち込みたいけど何に打ち込むのか?大学入学後の,掴みどころのない漠然とした不安は自分の居場所の不在によるものでした。新歓の前日の夜,歯を磨きながら「もしかしてボート部に入れば自分の居場所があるかもしれない。俺はボート部に入ってしまうかもしれない。」と思ったのを覚えています。結局次の日,人生で初めて乗ったエイト,京大ボート部の居心地の良さ,年中合宿生活,琵琶湖周航などの過剰な魅力に引き込まれ,予想通り入部宣言をすることになりました。「うお,うお,うおおおおおええええいい!!」というあの声に囲まれながら,これでいいんだ,ここで4年過ごすんだ,と心の底から安心したのをはっきりと覚えています。新歓で喋った先輩には,高校時代,高2秋がピークで,それ以降探究が忙しくてなかなか冬練に参加できず,そのまま春で引退してボートをやり切れなかった,と言った気がします。でもそれは入った理由というより,入部の背中を押してくれたものの1つで,結局は居場所が欲しかったのが1番の理由でした。
ボート部に入って,想像していた通りの濃い関係ができてきました。3階の,一見散らかっているようで,必要なものは全て布団から手を伸ばせば届く範囲にある,最適化された空間も,まるで実家かのような安心感を与えてくれます。合宿生活は最高です。これでいいと思っていました。ところが6月頃から練習がしんどくなってくるにつれ,心の奥底で,自分が高校でボートを引退するときに言った言葉が引っかかっているのを感じました。「僕はボートが好きですが,その何倍もボート班が好きです。夏の川やエルゴで,ボートそのものが嫌になったことは何回もありましたが,ボート班が嫌になったことは一度もありませんでした。」自分は本当にボートが好きなのか?膳所高ボート班とか,京大ボート部が好きなだけで,実は競技自体はそこまで好きじゃなかったのではないか?
高校時代を振り返ってまず思い出すのは,練習後に艇庫でダラダラしたこと,遠征先で温泉に入ったこと,艇庫に泊まったことみたいな(ボート班)かつ(ボート競技以外)ばかりでした。もちろん,高2の秋に県予選を突破し,近畿大会まで行ったことはボート競技の最高の思い出に残っています。それでも,やっぱり先に頭に浮かぶのは競技以外の思い出。私はこの事実に気づいていながらも,気づいていないふりを続けていたのでした。大学の部活も楽しいとは言え,目指す所はもちろん日本一。競技そのものが好きじゃなかったら4年間も続けられないということに怯えていました。

琵琶周オフ,とにかく退屈でした。夜は久しぶりに中学の友達とPCゲームで遊んで楽しい時間もありましたが,昼間は同期たちが帰省しているのをSlackで見ながらひたすらお布団でごろごろしていました。そんな時,ふとボートが漕ぎたい,と思いました。ただ退屈だから気晴らしにボートが漕ぎたくなったのだろうと思っていましたが,何故か分かりません,それ以降ずっとその状態です。オフが明けてから,練習がますます楽しくなってきました。エルゴでさえ,前向きな気持ちで漕ぐことができるようになりました。乗艇が,楽しくて仕方がありません。今になって,少しずつですが,自分が成長しているのを感じます。今はあの問いに自信をもって,「ボート部もボート競技も大好き」と答えられます。もちろん,また実力が停滞して考えが揺らぐ時期は来ると思います。それでも,ボート部が好きなままでいられたら,いつかはまたボート競技がもっと面白くなる,そんな日まで耐えられるはずだと思うようになりました。これこそが,ボート部でボート競技をする理由なんだな,と納得しました。
つい先日には秋季大会の選考がありました。私は目標にしていた1stエイトに乗ることは叶いましたが,2000mエルゴ7:00切りは達成できず,実力の足りなさを思い知りました。水上での500ttも,漕ぎが崩れたりなど,そもそものフォームの課題もたくさん見つかりました。1つの目標としていた選考も,終わってしまえば通過点の1つに過ぎません。これからは,大学に入って初のクルーで,新進気鋭の同期たちと共に経験豊富で頼れる先輩から沢山学ぼうと思います。これからまた講義が始まって忙しくなりますが,日々練習に励み,秋季は優勝します。がんばろういんぐ!!

適当に書いているつもりが,随分と長くなってしまいました。タイトルは,このTシャツの背中に書いてある言葉です。私は周りから見て,あまり何も考えていないように見えるかもしれませんが,実は結構いろんなことを考えながら生きているつもりです。この長くて拙い自己紹介を最後まで読んでいただきありがとうございます。
蛇足ですが,おまけとして夏休みに読んだ本の感想を書いてみます。読書初心者ですが,記憶の新しいうちに共有してみたいという試みです。暇で死にそうな人は読んでください。本は合宿所にあるので読みたい方いらっしゃいましたらいつでもご連絡ください。貸します。
1「金閣寺」三島由紀夫
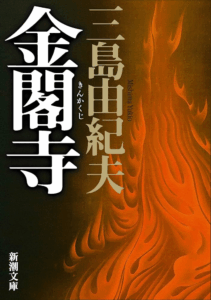
実際の金閣寺放火事件を基にしたお話です。観念上の,理想の金閣と実際の金閣との違いがストーリーを通して変化していきます。本当の美とはいったい何なのでしょうか。主人公が本物の金閣を初めて見た時,思っていた美しさが感じられないというシーンがあります。高校の現代文でも,理想と現実をテーマにした,ミロのビーナスは手がないから美しいという内容の文章がありました。自分には,ローイングにもそういう感覚があります。まだスカルだけですが,理想の漕ぎがあって,頭の中ではその美しい漕ぎができる。しかし実際にボートに乗ってそれを再現しようとしても,全くイメージ通りの漕ぎにならない。漕ぐまでは美しくても,漕いだらその美しさは失われてしまう。だからといって水上に出ずに脳内で理想の漕ぎを続けるのはおかしい。少しでも理想の漕ぎに近づけるように練習あるのみです。
2「暇と退屈の倫理学」國分功一郎

有名な消費と浪費の違いについての節が高1の現代文の教科書に登場し,面白かったので買いましたが,途中まで読んで長いこと放置していました。琵琶周オフの暇と退屈を抜け出すヒントが得られるかと思い2年越しに続きを読みましたが内容が難解でした。そもそもこの本は退屈の形式や性質についての考察がメインで,退屈を抜け出す実践的な方法を紹介するような本ではありませんでした。それでも興味深い内容ではありましたので理解している人いれば解説してほしいです。
3「成瀬は天下を取りに行く」(コミック) 宮島美奈 原作,さかなこうじ 構成,小畠泪 作画
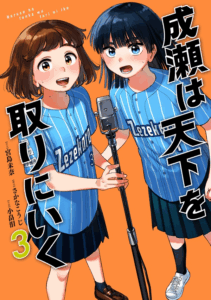
2024年に本屋大賞を受賞した小説「成瀬は天下を取りに行く」とその続編「成瀬は信じた道を行く」のコミカライズ版です。小説は続編まで高校時代に読んでいました。主人公は「200歳まで生きる」と宣言したり,髪の伸びる速さを測定するために高校の入学式で坊主にしたりするなど,かなり変わった女子です。幼い頃から多才で,色んなことにチャレンジしていきます。ちなみに舞台は滋賀で,なんと私は主人公と設定上膳所高校の同期です。滋賀のローカルネタも多く,滋賀県民にはもちろん,滋賀に詳しくなりかけの皆さんにもお勧めです。漫画には懐かしの膳所高校が細部まで描かれていてめっちゃテンション上がりました。でも個人的には,漫画はあくまでも小説を読んだ人が2次的に楽しむために作られた気がして,先に小説を読んだ方が面白いと思います。漫画にする上で削られた内容もありますし,京大も出てきます!勿論,小説も3階に置いてありますよ!
4「がんばっていきまっしょい」敷村良子
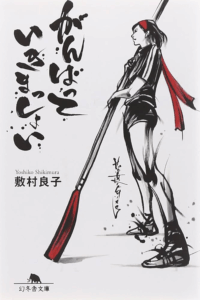
ドラマ化,アニメ映画化もされたひと昔前の小説。文武両道の名門校松山東高校が舞台で,女子部がなかった所から部員を集めて,ボート競技に打ち込む女子高生が主人公です。部活や進路,人間関係に悩みながらも日々健闘する高校生活が描かれています。ボート部員なら文字だけで脳内にはっきりと情景が浮かぶ細かな描写が魅力です。エルゴはまだなくてバック台だったり,付きクォドではなくナックルフォアだったり,時代を感じる点も面白いと思います。
5「レガッタ〜君といた永遠〜」原秀則
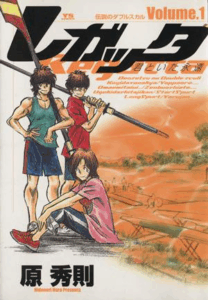
タイトル通りボート競技をテーマにした漫画で,ドラマ化されましたがそっちは完成度が低かったのか,低視聴率の為途中で打ち切られてしまったのが残念です。主人公の大学生大沢は,高校時代のライバル倉田と共にボート強豪校の龍王大学に進学し,1回生にしてダブルでインカレで優勝し「伝説のダブルスカル」と呼ばれました。大沢の幼なじみでマネージャーの操(みさお)と3人でオリンピック出場を目指す約束をします。ところが悲劇は起こり,倉田はこの世を去ってしまい,大沢はローイング界から身を引くことになります。競技と恋愛での複雑な人間関係が面白いだけでなく,レースの描写が本当にかっこいいです。直線2000mを繰り返し動作で漕ぐという一見地味なスポーツに見えるローイングの,繊細で奥深い所を見事に描かれています。「風の向こう側」など,現実のローイングを超えた(いや,私が到達していないだけで本当にあるのかもしれない)展開が激アツで,これをドラマで再現するのは至難の業だったことでしょう。読むだけで漕ぎたくなる,そんな漫画です。ちなみに,作品中に膳所高校ボート班がモデルとなった高校ボート部が登場します。確か艇庫には作者のサインが飾られていました。作中での艇庫周りの景色など本物そっくりで,見たときは思わず嬉しくなりました。
6「世界標準の科学的トレーニング 今日から始める『タバタトレーニング』」 田畑泉
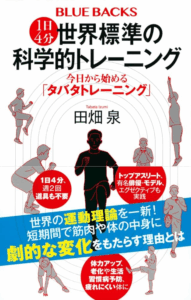
みんな大好きブルーバックス。著者はなんとあの「タバタ」さん。聞いたことがない人もいるかもしれませんが,タバタトレーニングとはエルゴとかジャンプサーキットなど,短時間で疲労困憊に至る高強度でのトレーニングを20秒on10秒offで6~8セット行うトレーニングのことです。この本では,このトレーニングがどうして効果的なのかを,体内で起こっている反応や実験結果のグラフなどを用いて,科学的に詳しく解説されています。私は一応高校生物は専門まで履修しましたが,ATPとかクレアチンリン酸とか,何となく聞き覚えあるなあくらいまで忘れていました。それでも読み進められるように,わかりやすい工夫が様々されています。ハイブリッドカーが発進時にモーターを用いて,動き出して来たらエンジンに切り替えるという例えを用いて,運動開始直後は無酸素性のエネルギー供給源からエネルギーを得て,しばらくしてから有酸素性の方に変わることが解説されていたりなど。この知識は知っている人も多いかもしれませんが,大体どれくらいの強度でどれくらいの時間運動すれば有酸素性の運動になるとか,それぞれのエネルギー供給源の特徴はどうかとか,そこまで詳しく知っている人はあまり多くないかと思います。エルゴのメニューを考えたり,レースのプランを考えたりする上で有益な情報が多いです。ただ無心で練習をこなしていると,何のためにやっているか分からなくなりがちですが,今自分は何を鍛えていて,このメニューを乗り越えた自分はどう強くなるのかが明確に分かっていると,メニューとの向き合い方も変わります。
ここまで読んでくれた方,本当にありがとうございます。同期たちが2000字に届かへんとか口々に言ってましたが,思いついたら書き足してを繰り返した私は気づけば1万字近く書いてました。内容は大して濃くないのに字数だけ多いブログとなりました。でもまあ,あの徒然草でさえ,2,3行で終わる段もあればページを跨ぐ段もあったので,ちょっとぐらい長いブログがあってもいいよね!
それでは次のブログ,いつになるか分かりませんが,その時また会いましょう!
