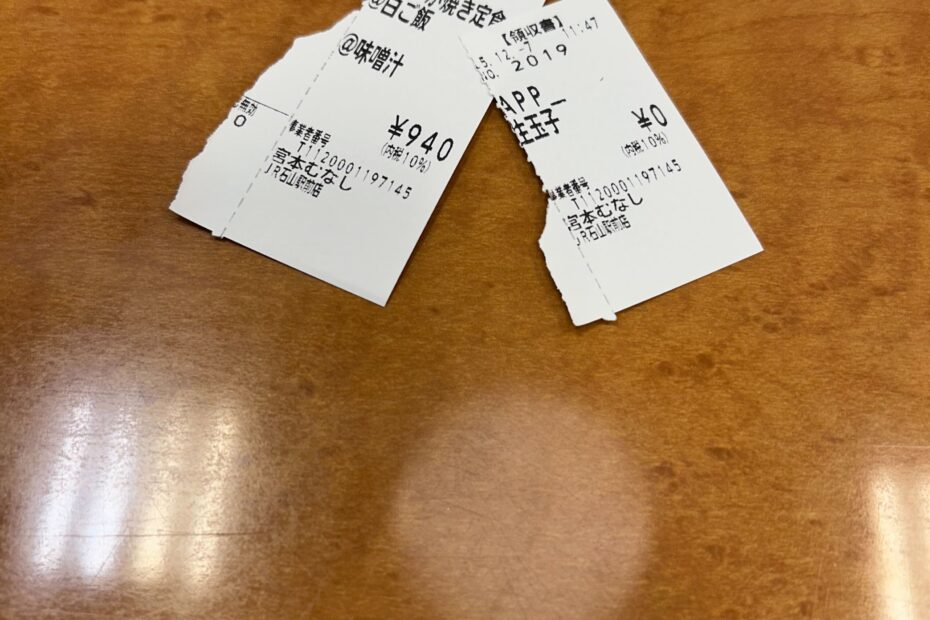M-1は点数をつけるコンテストではなく年1の漫才番組として見ることで精神衛生を保っています。どうもこんにちは、いむらです。やっぱ今田さんの回し、笑い泣きと上戸彩のさっと切り上げる進行。これを見ないと年を越せない。
一応、年末なので今年の振り返りブログと銘打っておく。
映画についてはアニメーション作品がとっても楽しかった。「チェンソーマン レゼ編」、「ひゃくえむ」を同じ日に見に行ったり詰め込んでみたわけだが、楽しすぎた。「ひゃくえむ」とか原作含めてたっぷり楽しめたし。ただネトフリ独占配信かぁ、となっている。ネトフリといえば1月につよつよクリエーター山下清悟さんの初監督作品「超かぐや姫!」があるが、映画館でやらないのに映画と銘打っていいのか…?となってしまっている。ただsupercellのryoが参加と聞いた時点でもう見るしかなくなってしまっているのだが。他にはエヴァの「シト新生」と「Air/まごころを、君に」を映画館で見れてよかった。キャラクターの気持ち悪さが染み渡る。整う。「メダリスト」「閃光のハサウェイ」、ジョジョ7部、「チェンソーマン 刺客編」の予告も出てハッピー。馬、結構よさげ。
音楽については「サンフェーデッド」。篠澤広、長谷川白紙の誕生日一緒コンビの2曲目。サンバ調に仕上げた「光景」とは一風異なった楽曲。2000年代のオルタナロック、節度のないディストーション、露光のきいたMV、そしてそれらと対照的な儚い彼女の歌声。あの楽曲は様々な人々に「存在しない記憶」を呼び起こした。例に漏れず自分もその日は衝撃のあまり、なにものどを通らなかった。これが彼女のコアなのか。
あとは星野源の「いきどまり」。映画「平場の月」の主題歌であるが、これは本当に言葉じゃ言い尽くせない良さがあって、星野源の才能にまたのど元を引き裂かれた。「さようなら」史上一番響く「さようなら」だったと思う。今回挙げたこれらのアーティストに対してはファンになってしまってはならないという生存本能が働いてしまう。
他には最後のエルゴとかだろうか。心をルネにとらわれすぎている。
そしてなんだかんだ、やぱありデカかったのは新人戦。多少脚色しつついい感じに考えが広げられそうなので、文字にしてその助けにしたいと思っていた。ただなんだか書き進めていると至極当然のことすぎて、書き進めるのがあほらしいし、だんだんポエミーな仕上がりのエッセイになってきてしんどくなってきた。多少人が読めるような文章は心がけはしたが、付録にしようと思う。はじめてブログのために書庫行ってまで本を借りたよ。アーネストベッカーの「The Denial of Death」。ピューリッツァー賞を取ってるらしい。というかこういう観を書くのって今みたいな貧弱な状態じゃなくて、ある程度芯が固まったときが一番いいと思う。ただそれは何時なんだという話になってしまう。こうぐるぐるするのが悪い癖。電子かよ。こういうことを書くからこじらせてるだの、結婚できないだの書かれるわけ。
大した結論に至ったわけでもない付録、以下。
個人として紆余紆余曲足踏足踏折折折くらいあっての新人戦クルー結成だった。最初はうぉ、となる状態でSやCが不満持ってそうだなと回艇のたびに取り繕っているかのような声色やらで感じていた。不安にならないようにふるまってくれているだろうに、またはそう思い込んで云々考え込むというのはヒトの面倒なところだと。とりあえず駿が勝てるクルーになるかどうか自分に懸かっていたのは明白であった。オッ盾に空海乗ってたとはいえ、関選、東大戦の空海には一緒に乗れていなかったわけで、平井清水とは初。それ以前に上手くないし。ただそこまで詰められた状況でも、自分はこの競技を皆と比べれば、そこまで愛していないのでおそらく没頭できるほど賭けれてなかったように思う。新人戦対校に選ばれたんだから腹くくれやとも思うが。でもなぜか3番としてただただSの動きに合わせることに専念することができていた。この矛盾を遂行する原動力の正体はもう結論は出ててみんなで勝ったり負けたりしたいから。もっと言えばひとりで負けたくなかったから。そんな云々があって1か月程度練習して、京都レガッタでの優勝、TTなどを通して、それなりにいい感覚を瀬田で掴んで戸田へ向かった。
しかし、そんな中で臨んだ予選の漕後感は、それはもうひどいものだった。
奥歯は痛く鉄の味。頭も痛む。視界はぼんやりと白濁し、いつもは大きすぎるくらいに感じるCOXの声さえ、その時は耳に届かなかった。乳酸だのありふれた疲れなどではないものに覆われていた。何かが根本から削ぎ落とされるような感覚。ただ、ひたすらに、苦痛だった。その後の風呂は例のコメントの話も聞いて溜息まみれの状態。ー「でも…風呂って嫌な事を思い出すほうが多いよな。」 それも含めての命の洗濯なのだろうけれど。ー
ところが、中日を空けての準決勝、そしてB決勝は違った。ひどく心地が良かった。
京都レガッタの際にあった足の震えや、予選にあった行き過ぎた緊張感とは打って変わった静謐な空気が、自分に、駿にあったように思う。ー空気がひりひりしているー個人としてはおそらく、先のレースであった「勝たなければいけない」という強迫的な使命感が欠落していたからだろう。もっと正直に言ってしまうと、その根底には相手が自分からしてみれば格上の大学であることによる、ある種の「諦め」があったのかもしれない。それがうまく好転したのだろう。結果としてその諦めは、ネガティブなものとはいえネガティブなものを生み出したりはしなかった。ただこの瞬間に最善を尽くして、楽しみたかった。2000m、240本を良い水準で遂行できたという確信。
平井は―勝手に解釈させてもらうが―この時のあらゆる体の疲れその他脳に届くあらゆるモノの心地よさへの反転、スポーツの真髄とも呼べる感覚を「生きてる」と形容している。もととなった真波山岳もそういうことを言いたかったんだろう。整調としてコンスタントSR38出し切っちまったのだから、そりゃあそれくらい生命を感じてくれないと浮かばれない。非常に頼もしい限り。だが一方で、自分は「死ねる」という感情が漕ぎ切ったときに生まれてきた。先の爽快なものと比べれば、私の抱いた感情はなんとも物騒な文字面である。でもそれは単なる絶望などでは断じてなく、究極の充足感だった。準決勝、B決勝も1着でブザーを鳴らせたわけでもないのに。
格ゲーでいえば相手の練りに練られた厳しい攻めをしのぎ切ったあと、狭い逆択を通して自分の攻めの番がまわってきたかのような感覚。ドット単位の体力で、端を背負った状況パニカン最大コンボを叩き込んでいる時の愉悦。まぁ少々言い過ぎな表現ではあったが、もっと身近なものでいえばサウナの後の整いに近いものかもしれない。
しかし、PCの電源を切れば静寂が戻り、サウナから出れば乾いた空気の帰路、陸に上がればその充足感とやらも霧散する。なんと代謝のいい器官なことか。
静謐な水上とは異なり、陸に上がればこの世には多くのもので満ち満ちている。
街に出ればたくさんの人。図書館に入ればずらり並ぶ本。街の背の高い店に入れば何体ものマネキンがその季節の正解を提示し、駅の地下へいけば、何種類ものごはん屋さんが魅惑の匂いを垂れ流す。映画館にでもよれば、何十もの映画が1日に放映されている。
もちろん唾棄すべきものはあるにせよ、自分の哲学にとって真理たりえるものなどごまんとある。だが、それを全て消費し、わが物とすることは物理的な時間とキャパシティの限界ゆえに勿論不可能と言い切ってよい。こちら側から何かを書き、練り上げたコンテンツを公に出すことなど二の次だ。世の中のなにかしらを作り、こちら側へ提供してくれる人には頭が上がらない。
これだけものが増えると、良い物悪い物を早々に選別する必要が生まれてくる。もしくはよかれ悪かれ早々に食う必要がある。後者は俗にいう「ファスト文化」であるが、これには限界があるため、前者を選ぶ人間の方が多いと考えるのが自然。それなら生み出す側も「これは面白いよ!」と派手なフックを用意しないと商業的にうまくいかない。何回も見たくなる映画を選ぶとして、。一目でわからない映画が正解であるといいたいわけではない。その映画だけで伝えたいことが完結し、抽象的テーマがありふれていて、だが刺さるものかつ、具体的テーマが新鮮であるものが自分にとっては十分三ツ星なのだ。だがそれを吟味することで価値が生まれるのも確か。それさえもコストとして捨ててしまう人もいるらしい。
ただ、なぜ世界はこうも「分かりやすく、効率的」になってしまったのか。それは、法を理解し、ルールを理解することが、この世界で生きていく最低条件だからだ。ルールと環境が変われば、その中で生き残るための「人にとっての最適行動」も変わっていく。環境決定論というと少し語弊があるだろうか。現代という環境において、最も効率よくインセンティブを得るための最適行動。それは、「失敗しないこと」。
あえて主語を大きく言わせていただくが、人はいつからかネガティブになっていく。子供の頃のような無鉄砲さを捨て、突っ走って大きなマイナスを被ってしまう前に踏みとどまる、そこまで踏み込まない。それは生物としての生存戦略としては「賢い」し、大人になることの肯定的な側面でもある。だが質が悪いのは、現代社会ではその「事なかれ主義」こそが、最も効率よくちまちまとインセンティブを得られてしまう点にある。 傷つかず、疲れず、そこそこの正解を選び続けること。それが最適解とされる環境の中で、我々の魂は摩耗していく。あのボートの上で感じた、実感はこの最適化された日常のどこにも落ちてはいない。こんなことを言う自分もこのブログにおいてだってたびたび予防線を張っているのだ。自分の考えを表に出す責任とやらをまるで感じられない。
(新劇場版エヴァ・破においてシンジは使徒に侵食されているアスカに対し殺したくないという思いが先行し、戦って助ける方法を模索することを捨てた。そこでリスクを負って介入することを選べなかったシンジはそこでQやらシンやらにアスカとのもつれを引きずってしまっている。そしてそこに気づくことで大人への一歩を踏み出す。自分のこの流れだと現代社会はその先行した思いも肯定すると考えられるが、命がかかわるとさすがに傾くだろうとも思う。ここの塩梅はよくわからない。みんな経済人ではないのだからそりゃあ当然なのだが。)
寒さに震える必要も、飢える心配もない。ただ、用意されたインセンティブに従って、リスクを避けて歩けばいい。環境がそう決定づけているからだ。突っ走って大きなマイナスを被るよりも、踏みとどまって小さなプラスを得る方が「賢い」と、この環境が囁き続けている。
先日、とあるインタビューを見た。日本、ひいては世界の格ゲープロシーンのパイオニアたるウメハラ選手、そしてときど選手(REJECT所属)のインタビューである。そこでウメハラ選手がこう述べる場面があった。
「キャリアが長くなるとどうしても大づかみになってくるところがある。若いときは、そのゲームタイトルが終わる実感がなくずっとやろうという気持ちでいて、事細かに取り組んでいた。しかしある日新作が出た時、それまで積み上げたものがばっさり意味がなくなる。これを幾度となく経験してきたため、今では要領よくやってしまう。」
そして彼は、こう締めくくった。 「好きなことなのに、なんて大雑把にやっていたんだろう」
この言葉は深く刺さった。
まさしくプログラムによって完全に征服された世界で戦っており、効率化・最適化ということに最も敏感に、最も真摯に取り組んでいるはずである。その人をもって広範な部分にこだわることを大雑把と悔いている。経験を積み、新作が出るという環境のリセットを知ってしまったからこそ、傷つかないように、徒労に終わらないように、「要領」という名の効率化を身につける。だが、ウメハラ選手の凄みは、その効率化を成長とするのではなく、ある種の妥協のように捉えている点にある。要領よく練習に取り組み効率よく勝つことよりも、非効率でも事細かに没頭し、繰り出すプレーを80点から100点のものにすることの方が、人生の解像度が高いことを彼は知っているのだ。
ポジティブというか、リスクがあること、もしくは成功のステージまで到着するまでの苦しみがあることを理解してもなお、自分を壊し再構成していくことのできる人間は尊い。そういう挑戦を選べる人間を天才だとかスターだとか呼んでやりたい。ー辞書に載っている通りの「天才」というのは地球上の物に適用するに四角の型に丸を入れるような歪さを感じる。ーただ、そういう人間はその美しさ、尊さを誇っているとも限らないというのがまた。それもまた彼らの美点でもあるのだが。
彼らにとってそれは、美学というよりは、呼吸をするような生存本能に近いのかもしれないからだ。昔、そろばんを習っていた小学生の時、県大会に出たことがあったのだがそこではトーナメントに参加していた。その前に行っていた六種目総合の点数を小学生全員で競うやつで優勝した小学5年の男子とトーナメントで当たってぼろ負けして、そのあと軽く雑談する機会があったのだが、なかなか空気が違った。自分もなかなかこの分野に没頭できていると思っていたが、彼の暗算の練習の仕方や大会への取り組み、速さの追求。それを嬉々として話していたところを背筋を凍えさせながら聞いていたことを10年以上経った今でも覚えている。彼にとって艱難辛苦とは相棒なのだ。
天才論について語りだすと、漫画『ハイキュー!!』のせいで思考が無限に発散してしまう。この作品は「バレーを未来にする人間」と「バレーを過去にする人間」の接点を見事に描いており、自分はこれを愛してやまないのだが、全てを語ると課題をやる時間がなくなるので、ここでは一人の登場人物の言葉を借りるに留めておく。作中に登場する強豪校の主将、北信介は「天才」と呼ばれる後輩たちについてこう語る。
ーーー毎日一から十やっとるところを、侑みたいな連中は一から二十やっとんねん。あるいはより効果的な十、密度の高い十、ほんでたまに、一から十やなくて、AからZやってみたらどんなやろ、おもろいんちゃうかって考えたりするやつらなんや。(中略) 世の中、かなわんと思う人たちはいっぱいおって、そういう相手を凄いなあと思うのは当然や。突っ走れることは才能やと思うし、あいつらをなんて呼んだってええねん。天才は悪口やないしな。 けど、あいつらのこと、最初から優秀なんやと思うことは、勝負するまでもなく負けとるっちゅうことやし、失礼やと思うねん。 (『ハイキュー!!』より引用・要約)ーーー
多くの人は環境に従って、環境に最適化された行動(ネガティブ・リスク回避)をとる。「1から10」までを効率よくこなそうとする。しかし、天才と呼ばれる人たちは、環境に支配されない。彼らは「1から20」をやり、「AからZ」を試す。与えられた環境を限界と捉えず、あくまで素材として利用し、自らの意志で世界を常識破りに再構築する、いわば「環境可能論」の実践者といえよう。
翻ってのあのレース。あの時私は、勝たなければならない状況や上手くない自分という空気を、無意識のうちに破壊していたのかもしれない。効率よく漕ぐことや、ペース配分という「要領」を棚に上げた思考で、ただただ前の動きを参照するというか均衡を崩さないことに神経を働かせる。それでいて自然に結果的に楽に漕ぐ。そのときはじめてボートに乗って240本漕ぎ切って、世界が鮮明な像を結んだように感じる。だからこそ、あの「死ねる」ほどの充足が訪れた。
『決定論』に従って、環境に最適化された行動(ネガティブ、リスク回避)をとるべきであるように思う。しかし、天才やスターと呼びたい人たちは『可能論』の実践者だろう。彼らは環境に支配されず、環境を利用して自らの意志で世界を再構築するように自分は思う
破壊なくして、創造はない。死(終わり)を意識しない生に、鮮烈な色彩は宿らない。
破壊の果てに、何が残るのか。先で示したような、既存のルールや自分自身を破壊し、再構成する行為。そのプロセスを経て現れるのは、すべてが説明され尽くした窮屈な正解ではない。むしろ、そこには広大な「余白」が生まれる。そして私はその余白を愛したい。
ここで視点を、勝負の世界から芸術、あるいは表現論へと移したい。第2章で触れたように、現代社会は「分かりやすさ」と「効率」で満ちている。隙間なく情報が詰め込まれ、受け手が解釈する余地など1ミリも残されていないコンテンツこそが「親切」で「良質」なのだ。だが、本当に心を震わせる表現とは、そういうものだろうか。
芸術における「余白の理論」というものがある。 それは、「描いた部分」と「描かない部分」の関係性のことだ。すべてを言葉や色で説明し尽くすのではなく、あえて描かない部分を残すことによって、受け手(他者)や環境が入ってくる隙間を作る。 そう、やはり自分で提示するのは「わずかな手がかり」だけでいいのだ。李禹煥は「余白の芸術」でこのように冒頭を進めていた。
ーーー
内部と外部が出会う道である。そこでは私の作る部分を限定し、作らない部分を受け入れて、お互いに浸透したり拒絶したりするダイナミックな関係を作ることが重要なのだ。この関係作用によって、詩的で批評的でそして超越的な空間が開かれることを望む。私はこれを余白の芸術と呼ぶ。
(中略)
だから描いた部分と描かない部分、作るものと作らないもの、内部と外部が、刺激的な関係で作用し合い響きわたる時、その空間に詩か批評か超越性を感じることが出来る。芸術作品における余白とは、自己と他者との出会いによって開く出来事の空間を指すのである。
李禹煥の「余白の芸術」より引用
ーーー
ある程度フックのようなものをひとたび作ってしまえば、それによって、その周りの自分が関係していない様々なものが、あるいは作っていない色々なものが、急に雄弁に語りだす。「作らない周りのいろんなもの」が、こちらが提示したわずかな核に反応し、大きく反響して一つの表現の世界を形成してくれる。それは雪の結晶のように、自己完結した秩序だった美しさとは違う。もっと動的で、予測不可能なもの。例えるなら、静まり返った大聖堂で鳴らす拍手のようなものかもしれない。ボートに関することでいえば、モーターボートの作る波だとか?ともかく、芸術作品における余白とは、単なる何もないスペースではない。自己と他者、あるいは自己と世界との出会いによって開く「出来事の空間」を指すのである。
これは、芸術だけの話ではない。人生にも適応できる理屈に勝手に取り込みたい。全てを手に入れようとするのではなく、「限界(余白)」があるからこそ、その空間に詩や批評が生まれるのだと。私たちは、人生を満足するために何か(金、地位、知識、あるいはフォロワー数も?)で埋め尽くそうと必死になる。空白を恐れ、沈黙を恐れ、常に何かを消費し、何かを発信し続ける。だが、全てを手に入れ、全てをコントロールし、全てを埋め尽くすことなど不可能だ。むしろ、「限界(余白)」があるからこそ、その空間に他者が入り込み、詩やドラマが生まれるのではないか。 あのレースで私が感じた「死ねる」ほどの充足感も、逆説的だが、私の肉体の限界という余白がもたらしたものだったのかもしれない。自分の意識ですべてをコントロールしようとする浅はかな万能感を捨て、肉体の限界を超えて意識が「空白」になった時。その余白に、艇の進む音、水の抵抗、仲間の呼吸といった「世界そのもの」が流れ込んできた。私が艇を進めていたのではない。艇と、水と、私たちが、余白の中で一つに溶け合っていたのだ。描かないことで、世界はより鮮明に見えてくる。 絵画にキャンバスの端という「物理的な限界」があるからこそ、その中の絵筆の跡が意味を持つのと同様に、私たちの人生にもまた、それを作品として成立させるための絶対的な枠線が必要なのだ。我々の生涯における最大の「描かない部分」。逃れようのない絶対的な「余白」。
それを私は「死」としたい。
どれほど効率的に生きようと、どれほど素晴らしい作品を残そうと、生物としての絶対的な終わりは必ず訪れる。文化人類学者のアーネスト・ベッカーは、著書『死の拒絶』にて、人間は死の恐怖から目を背けるために文明や文化を作り上げたと説いた。だが同時に、人はその生物として絶対の死に、どこかで向き合わなければならないとも示唆している。
その「終わり」は、いつだって日常のすぐ隣にある。ニュースで流れる訃報、愛したペットの冷たさ、警察署の前に掲げられた看板の数字、友人の報せ、そして肉親。どのタイミングで、どの順番で訪れるかは人それぞれだが、それは確実にそこに在る。その死に対して、我々がすべきことは何だろうか。喜悦であろうか。悲嘆であろうか。いや、そのどちらでもない。「理解」である。
現代のテクノロジーやフィクションの世界を描くいくつかのSF作品では、義体化や精神のデータ化によって生物としての限界を克服する道が提示されている。魂の行方だとかだが、それゆえの法の行く先だとか。その他いろんなテーマがあらゆる作品で扱われていて物語としては非常に面白いし大好きだと思う。ただそれが現実のものとなり実現するまでに、私はこの世を去ってしまいたいというのが本音だ。病気や怪我を健康に戻す医療ならまだしも、定命の生をプラス永遠や能力拡張へ持っていくトランスヒューマニズム的な思想はどうも気に食わない。生物として、人間として、生への執着や欲にあらがえないことは理解できるし、見えていないだけで自分も土壇場になれば縋るのかもしれない。
それでも、私はささやかなレジスタンスを掲げたい。医療の発展はまさしく「死の克服」をいつか象徴することになるだろうが、自分はそれを、人間に寿命をプラスするものではなく、月並みだが「家で死ねる未来の提供」と解釈したいのだ。病院のベッドでチューブに繋がれて「生かされる」のではなく、自分の愛した空間で、自分の人生という作品の「余白」を受け入れること。
少々筋とずれてきたが、なぜそこまで死にこだわりたいのか。それは、死を見つめることで、逆説的に「生き方」の解像度が上がるからだ。
終わりがあるからこそ、物語は美しい。枠があるからこそ、絵画は絵画たりうる。もし人生が永遠に続くなら、今日という一日は無限の中の無意味な一粒に過ぎなくなる。だが、終わりが確定しているからこそ、今日をどう生きるか、今この瞬間に何を感じるかという問いが、ぼんやりとした輪郭から鮮明な像へと変わる。
私が感じたあの「死ねる」という感覚。あれは、その日の生をその日の中でもうまく理想的ともいえるくらいに実行できて、生の解像度が極限まで高まり今日に満足できた瞬間だったのだと思う。そこで感じたあらゆるものがそれの強烈な証だった。効率化された日常では決して味わえない、生の触感。それを手にするために、私たちはまた自分を壊し、非効率な熱狂へと身を投じるのだろう。なんだ、違うと思っていたら一緒じょのいか。
産んでくれと頼まなくても堪能できるこの人生、好きに生きようではないか。
不確かな未来に怯えて縮こまる必要はない。どうせ最後には、大きな余白が待っているのだから。その時が来るまで、私は私の「描いた部分」を、泥臭く、非効率に、けれど愛おしく積み上げていこうと思う。