お疲れ様です。いつも応援ありがとうございます。二回生漕手の井村です。最近、三島由紀夫の本を読んでいるので、ある程度メンバーについての情報をまとめてGeminiに入力し、三島由紀夫風の文章として出力してもらいました。多少粗削りですが、やはり便利ですね。
S 平井雅治

その整調は、いかなる水面の揺らぎにも、いかなる精神の昂ぶりにも侵されぬ、不動の儀式であった。彼は駿という男の聖典を読み解き、その一挙手一投足に宿る神託を理解し尽くしている。だがその脳髄は、先代の仲間たちが遺した夥しい教義の数々によって飽和し、今や美しくも混沌とした地獄を内包していた。不動のリズムを刻み続けること、それ自体が、内に巣食う混沌に対する唯一にして悲壮なる反逆であったのだ。
3 井村敦

彼の情緒は、およそ高尚とは呼び難い、低俗な電子の残像を摂取することでのみ、かろうじてその平常を保っていた。魂の平衡を保つためならば、人は時に毒をも喰らうのだ。氷上の覇者の栄光を描いた物語を読了し得た一時の昂揚も、所詮は泡沫。昨年のおのれの姿が、大義を謳う広告に使われている様を目にして、彼は何を思うか。過去という名の、もはや手の届かぬ場所に剝製にされた自己の幻影が、そこにあった。
2 清水瑛俊
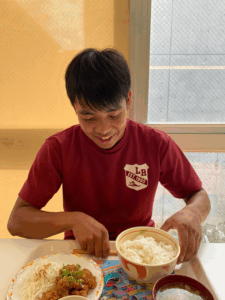
あの男が、ボートという存在に対して、いかなる信仰を、あるいは冒涜を抱いているのか、未だ誰にもうかがい知ることはできぬ。それはあたかも、己に断じてその気はないにもかかわらず、相手の女が純白の衣を幻視し、永遠の誓いを期待しているかのごとき、残酷な緊張関係に似ていた。彼の魂が抱えるであろうその入り組んだ葛藤の片鱗も見せぬまま、彼はただ無機質な電磁気の実験に身をやつす。生きろ、強く。その苦悶こそ、生きていることの証左なのだ。
B 長嶋洸司郎

彼は我々の精神の「父」であった。クルーというこの仮初の家族において、彼は揺らぎなき屋台骨であり、その存在自体が掟であった。当初、彼の肉体を蝕む古傷の亡霊が我々の脳裏をかすめもしたが、時はその懐疑を静かに抹殺した。彼の強靭な肉体と精神の前では、不安という脆弱な観念は、その影すら残すことを許されなかったのである。
C 西尾智志

彼は「国体」という晴れ舞台を踏み、そして豪奢なホテルの清浄なシーツに身を横たえるという、束の間の王者の夢から覚めたばかりであった。その栄光の残滓を身にまとったまま、彼は労働という日常の泥濘に足を踏み入れる。俗世の客が発する無価値な言葉の礫に、彼の魂はかすかな傷を負い、萎んでしまった。天上の輝きを知った者ほど、地上の退屈に深く絶望するのだ。
クルーサポート
阪上由夏

彼女にとって言葉とは、内なる生命の発露そのものであった。彼女の口からほとばしる饒舌は、沈黙という名の死に対する、絶え間なき抵抗であった。その絶え間なき言葉の洪水が我々の魂に一時の光明を差し伸べる。やがて彼女が握るという鉄の円環が、彼女を、そして我々をいかなる運命へと導くのか。我々は彼女の新たな自己表現に期待せずにはいられない。
寺田知優

彼は啼く。その声は、苦悶か、歓喜か、あるいはその両方か。我々の鍛錬の場に、彼はその姿をひたむきに現し、その奉仕を捧げる。鉄の心臓という、文明の冷酷な塊を鎮めるための儀式で、彼の肉体は悲鳴を上げた。人体の要が、そのあまりの重さに屈したのだという。人の身がいかに非力で、しかしいかに美しく壊れ得るものであるか。彼の苦痛に満ちた呻きは、それを我々に教示していた。
コーチ
片岡さん
その知識は、収穫されたばかりの果実のように、豊潤な熱を帯びていた。我々が暗礁に乗り上げたとき、彼はその豊穣なる知識の中から、常に突破口へと繋がる一本の絹糸を、厳かに授ける。そして、我々がその糸をたぐり寄せ、僅かな光明を見出した刹那、彼の口からは、我々の存在そのものを肯定するかのごとき、熱を帯びた是認の言葉が与えられるのだ。その甘美な響きは、疲弊した肉体に新たな闘志という名の血を注ぎ込む、神聖な儀式に他ならなかった。
西尾さん
駿と舞鶴、ふたつの身体、ふたつの魂。常人であれば分裂しかねぬその責務を、彼は神話の英雄のごとく両肩に担う。その視線は、外界の光を歪ませるほどに分厚い硝子の奥から、我々の肉体と精神の最も深き場所を射抜くのだ。それはもはや「至高」や「究極」といった言葉すら陳腐に響くほどの、尊き意志の顕現であった。彼こそは、我々の目指すべき肉体と精神の、生ける理想像そのものである。